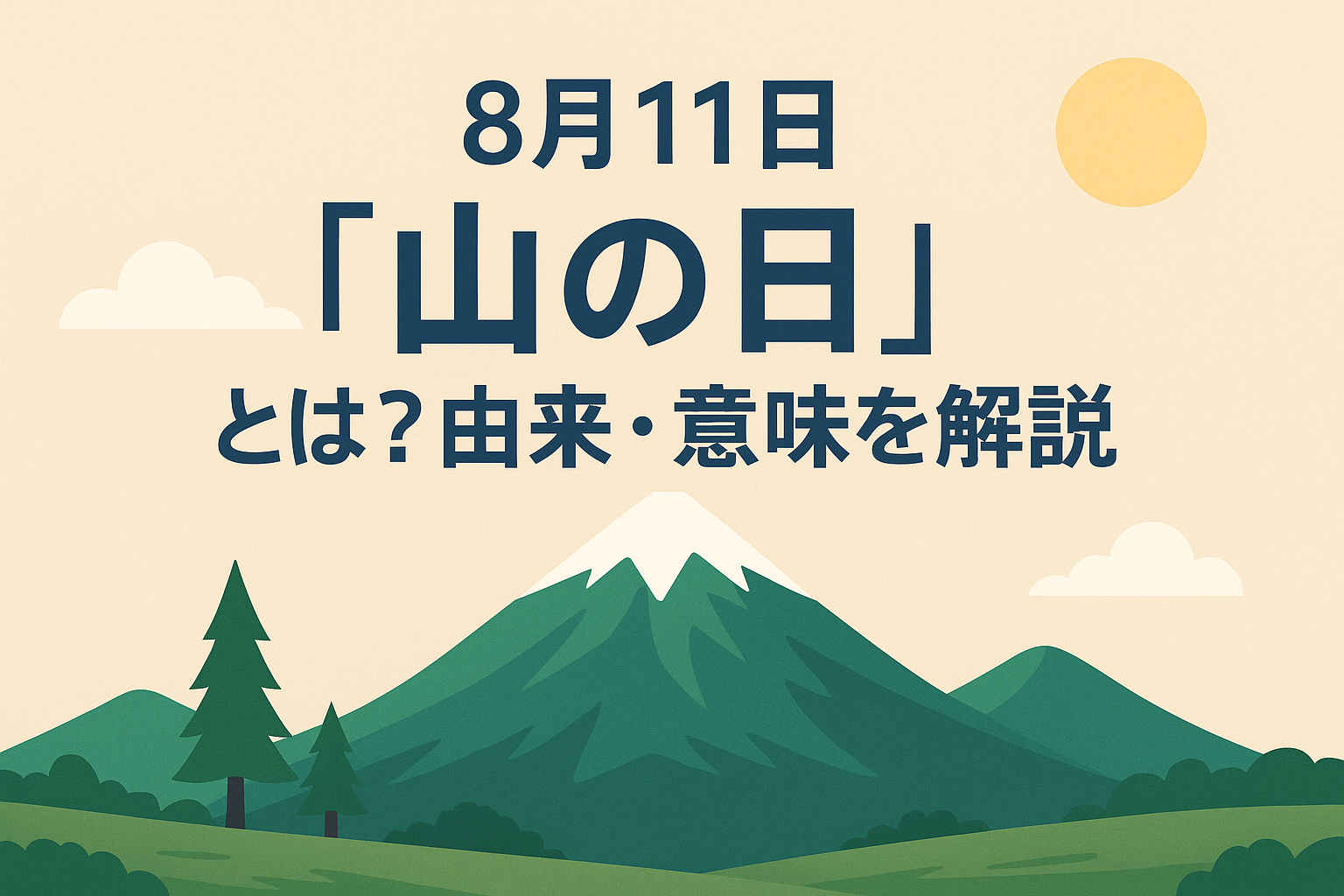8月11日「山の日」は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」という趣旨の、比較的新しい日本の祝日です。
制定は2016年とまだ日が浅いですが、その背景には「山の国・日本」として自然との共生や文化継承の意識が深く関わっています。
さらに、制定までには登山団体の長年にわたる運動、国連の国際山岳年、政治家らによる議連の立ち上げ、そして航空事故への配慮といった複雑な経緯がありました。
本記事では、祝日としての「山の日」の目的やその意義、日付が8月11日に定まった理由、登山を取り巻く制度や統計、社会的効果、そして現在の「ゆる登山トレンド」に至るまでを、わかりやすく詳しく解説します。
1. 山の日とは?目的と法的な位置づけ
法律上の定義と趣旨
「山の日」は、国民の祝日に関する法律において、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」日と明記されています 。
日本は国土のおよそ4分の3が山岳地帯で構成されており、山は生活の水源・資源・文化的背景として不可欠な存在でした。
その自然の価値を再認識し、未来への継承を促す意義も担っています 。
2. 山の日制定までの歴史的経緯
初期の呼びかけ~2000年代の動き
1961年、富山での登山イベントで「山の日を作ろう」との声が上がったものの制度化されませんでした。
その後、1992年にも山岳ガイドらが「登山の日」を提案しましたが、実現しませんでした 。
国連と登山団体の取り組み
2002年、国連が「国際山岳年」を宣言し、山と人との関係を見直す機運が高まりました。
2010年には山岳団体が連携し「山の日制定協議会」を設立 。
政治の動きと法制化
2013年には超党派の「山の日制定議員連盟」が結成され、祝日化に向けた動きが強まりました。
2014年に祝日法改正案が国会で可決され、2016年から「山の日」が国民の祝日として施行されています 。
3. なぜ「8月11日」なのか?日付選定の背景
お盆との連携と教育・経済への配慮
8月は祝日が少なく、教育日数への影響も少ないことから、夏休み中に自然とのふれあいを促す目的でも選ばれました 。
日航123便墜落事故との関係
当初は8月12日が有力候補でしたが、1985年の日航ジャンボ機墜落事故の慰霊の日であることから、避けるべきとの配慮で8月11日に変更されました 。
漢字の「山」由来の諸説
「8」の字が山を、「11」が木立を表すという説も広まっており、話題性を高めていますが、公式文書には明記されていません 。
4. 海外との比較・他国の山に関する記念日
調査の結果、日本のように「山の日」を国民の祝日として制定している国は非常に珍しいようです。
例えば、ネパールでは山岳崇拝や登山文化の尊重という観点で地域に祭りがあるものの、祝日とは異なります。
一方、ヨーロッパ諸国では山をテーマにした自然保護デーやイベントはあるものの、日本のような祝日としての制度化は例が少ないです(詳細な比較は今後の展開で)。
5. 登山・ハイキングの現状と統計データ
参加者数と遭難件数の推移
レジャー白書によれば、登山の参加人口は2017年 約650万人、2018年 約680万人、2019年 約650万人。
その後、2020~21年はコロナ禍で減少し、2022年は500万人に回復しました 。
また、2022年には登山中の遭難者数が史上最多の3,506人となっており、注意喚起の必要性が高まっています 。
年齢層別の登山行動
社会生活基本調査(平成23年)では、15歳以上で登山・ハイキング行動者数は約972万人、行動率は男性9.4%、女性8.6%。
とくに60~69歳層の行動率が高く、平均行動日数も年齢とともに増加傾向にあります 。
「ゆる登山」の現状
2025年の調査では、登山・ハイキングを気軽に楽しむ「ゆる登山勢」が約8割を占めています。
スマホを重要視する傾向は強い一方で、通信圏外の経験や事前確認の甘さなどからヒヤリハットも多く報告されています 。
6. 経済的・社会的影響
観光・アウトドア需要の喚起
山の日制定後、アウトドア方法への関心が高まり、登山関連需要に対し約8,200億円の経済効果が試算されました 。
さらに、ハイキングや観光プランとの連携により、地域活性化や関連市場の拡大も見込まれています。
高尾山周辺の動き
山の日には高尾山で登山技術講座や音楽イベントが開催され、京王電鉄高尾山口駅の乗降客数も増加傾向。
15年度には1日平均11,110人と過去10年で最大を記録しています 。
7. 安全対策と環境保全
増加する登山者に伴い、安全登山への啓発が重要視されています。
遭難事故防止のため、装備・計画・天候確認の徹底が求められます。
また、環境保全の観点では、トレイルの保護や外来種対策、ゴミの持ち帰りなど地域への配慮も不可欠です。
8. 山の日の現代的な広がりとイベント
地方・全国での取り組み
「全国山の日大会」は毎年開催県が変わり、2025年は福井県で文学展示や自然観察など多彩な催しが行われる予定です(詳細は今後公式発表参照)。
個人の楽しみ方の多様化
登山・森林浴・滝巡り・温泉・山岳映画・山菜料理など、山との触れ合い方は多様化しています。
またSNS映えするスポットや写真も若年層を中心に人気です 。
まとめと展望
「山の日」は、自然と共に生きる日本人の意識を再確認させる祝日です。
制定には登山団体や国際機関、政治家、地域社会が相互に関わった複雑なプロセスがあり、日付の選定にも多面的配慮がありました。
登山人口やアウトドア市場の活性化、安全性の課題、そして新たな楽しみ方の台頭など、社会的影響は多岐にわたります。
今後も「山の日」をきっかけに、自然との共生・文化の継承・地域活性化がさらに進むことに期待します。